
革財布の作り方Vol.2「つり」と「あり」のお話
2. 「つり」と「あり」のお話
革小物職人との会話でよく出てくる言葉に「つり」、「あり」というものがあります。あまり聞きなれない単語ですが、革財布・革小物を見栄えよく綺麗に、使い心地の良いものに仕立てるうえでとても重要な技術に関わる言葉です。今回はそれについてのお話です。
つりをとる

写真のパーツは二つ折り財布の表面になるパーツで、革の外面と内面を2枚重ねています。
右の手に持ったものは、外と内の革の寸法はまったく同じでまっすぐの状態だとぴったり重なり合っています。これを折り曲げてみましょう。
右の手に持ったものは、外と内の革の寸法はまったく同じでまっすぐの状態だとぴったり重なり合っています。これを折り曲げてみましょう。

すると内側の革が余ってしまい、膨らみが出てきてしまいました。
その一方、左の手に持っている方は外と内の革の長さが違うため中央が膨らんでいます。
これを折り曲げるとどうなるでしょうか。
その一方、左の手に持っている方は外と内の革の長さが違うため中央が膨らんでいます。
これを折り曲げるとどうなるでしょうか。
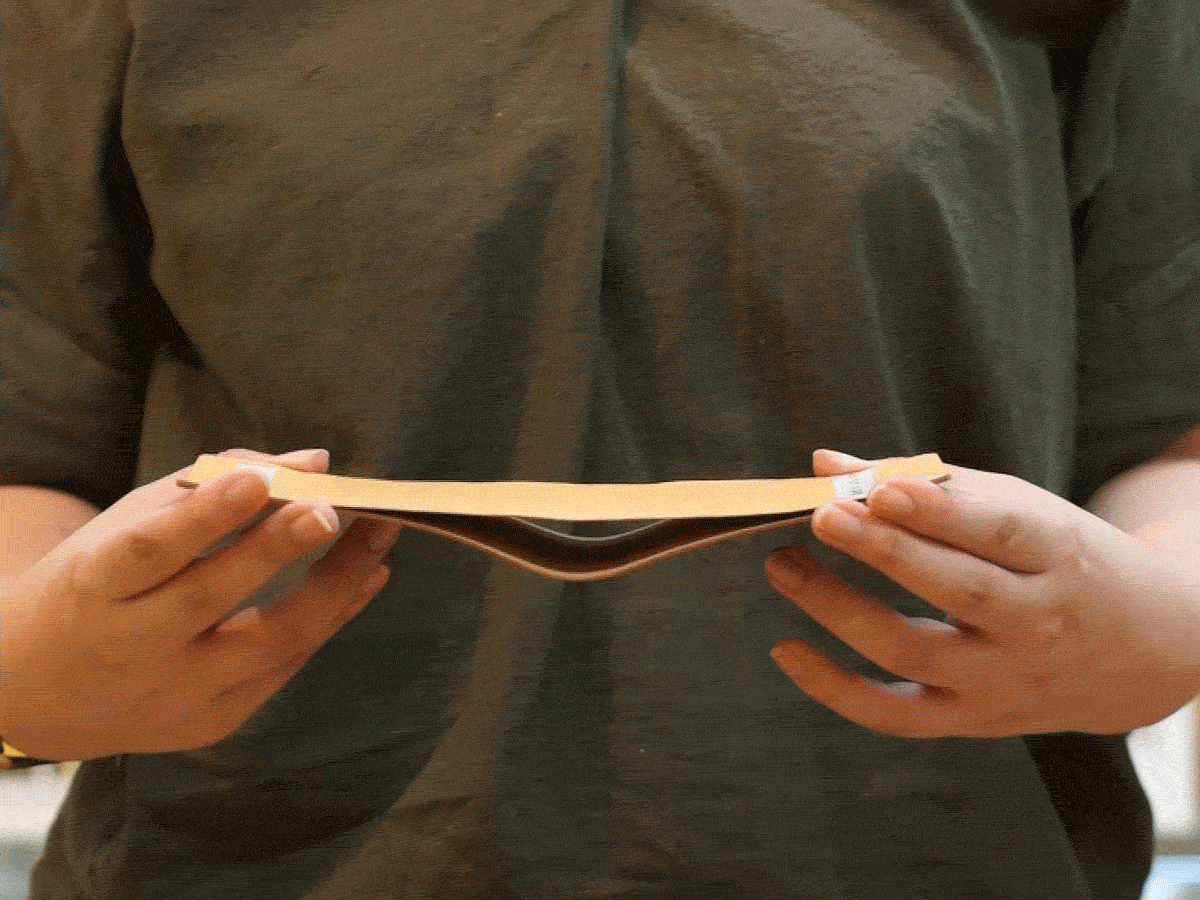
折った際に外と内の革がぴったり丁度良く重なり合います。
革財布や革小物は通常、本体やフタが曲がった状態になります。そのため、この左の方のように、革の外と内の寸法を変えて、折り曲げたときに無理なく綺麗に見えるように仕立てます。これを「つり」と呼んでいます。
革財布や革小物は通常、本体やフタが曲がった状態になります。そのため、この左の方のように、革の外と内の寸法を変えて、折り曲げたときに無理なく綺麗に見えるように仕立てます。これを「つり」と呼んでいます。

- この長財布はフタの折れ曲がる部分をつらずに仕立てたものです。内側の革が余ってしまっています。この「つり」を必要とする折れ曲がる部分を「あり」と言います。語源は不明ですが、職人には確実に通用する言葉です。
やっぱり厚みが命

さて、この「つり」をとる技術ですが、長さの差を出すのに明確な方程式はありません。ではどのようにしてその長さの差を決めているのでしょうか?
その答えは前回のお話と同様に、やはり「厚み」でした。
どういう素材で作るか、ー牛革なのか、豚革なのか(…etc)はもちろんですが、本体の仕立て方によってもパーツの厚みが変わりますその厚みに応じて、内側の寸法に対して外側をどのくらい長くする必要があるのかを、経験と感覚ではじき出しています。
その答えは前回のお話と同様に、やはり「厚み」でした。
どういう素材で作るか、ー牛革なのか、豚革なのか(…etc)はもちろんですが、本体の仕立て方によってもパーツの厚みが変わりますその厚みに応じて、内側の寸法に対して外側をどのくらい長くする必要があるのかを、経験と感覚ではじき出しています。

- 例えば、革を内側に折り返したパーツを重ねて縫い合わせる「返し合わせ」と革の断面を磨いて整える「切れ目」では厚みが変わりますので、「つり」の取り方が変わる。

- あるいはカードポケットの外にお札の仕切りが来て...、といったパーツがいくつ重なり合うかによっても取り方が変わる、といった具合に、その品物の仕様により微妙に変化していくのです。
一見するとそうした寸法の違いがわかりづらいものですが、一度そのあたりにも注目して品物を見ていただきたくとより一層革小物の緻密さを感じられるかもしれません。
Vol 2. 完

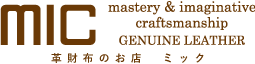

 mic
mic Hawk Feathers
Hawk Feathers ヒップポケット革財布
ヒップポケット革財布 大容量財布
大容量財布 ミニ財布
ミニ財布 エイジングギャラリー
エイジングギャラリー 読み物
読み物 春財布特集
春財布特集 製品レビュー
製品レビュー ヒップポケット革財布
ヒップポケット革財布 大容量財布
大容量財布 ミニ財布
ミニ財布 二つ折り財布
二つ折り財布 長財布
長財布 ミドルウォレット
ミドルウォレット がま口
がま口 小銭入れ
小銭入れ 名刺入れ
名刺入れ キーケース
キーケース カードケース
カードケース パス・IDケース
パス・IDケース スマホケース
スマホケース ポーチポシェット
ポーチポシェット ステーショナリー
ステーショナリー ケア用品
ケア用品 刻印について
刻印について 修理について
修理について レザーケアについて
レザーケアについて メールマガジンについて
メールマガジンについて ギフトラッピングについて
ギフトラッピングについて ショッピングガイド
ショッピングガイド よくあるご質問
よくあるご質問






